Channel:Health Geek
① 免疫系に関わるMICタンパク質(MHC class I-related chain)
これは MICA や MICB という名前で知られるタンパク質群です
主に免疫の働きに関与し、**ナチュラルキラー細胞(NK細胞)**を活性化させます
がん細胞やウイルス感染細胞に多く現れ、免疫監視の重要なターゲットになります
② ミトコンドリアに関係する MIC コンプレックス(Mitochondrial Contact Site and Cristae Organizing System)
ミトコンドリアの膜構造や機能維持に関わるタンパク質複合体です
エネルギー代謝や細胞老化にも関係する可能性があり、アンチエイジング研究で注目されています
• 運動と疾患リスクに関する研究
◦ 定期的な運動、特に筋力トレーニングは、心臓血管疾患、アルツハイマー病、パーキンソン病などのリスクを明らかに下げることが示されています。これは、運動が遺伝子レベルで若返りを実現し、細胞内のDNAエピジェネティック・リプログラミングを促進するためと説明されています
• 健康寿命を延ばす薬剤に関する研究
◦ 糖尿病治療薬のメトホルミンやラパマイシンといった薬剤が、健康寿命を延ばす薬として期待されています。しかし、これらの薬剤には筋肉の肥大を妨げ、筋力を増やす効果を減弱させる問題点が指摘されています
• 脳由来神経栄養因子(BDNF)に関する研究
◦ ウォーキングや水泳などの有酸素運動を習慣的に行うことで、脳の神経を成長させたり再生させたりするBDNFというタンパク質が脳内で増えることが、脳科学の研究で示されています。BDNFが増えると、記憶力の向上、感情のコントロール能力の向上、頭の回転の速さなどが報告されています
• 運動能力と脳の萎縮に関する研究
◦ ボストン大学の研究では、運動能力が低下していた人の脳は、定期的に運動をしている人よりも20年後に早く萎縮していたという結果が出ています。
• 片足立ちテストと健康リスクに関する研究
◦ 日本で行われた研究では、20秒以上の片足バランスが取れない人は、脳の病気や認知症のリスクが高まるとされています。ブラジルの研究では、10秒以上片足で立っていられない人はその後の死亡リスクが上がったというデータもあります。
• 歩数と認知症リスクに関する研究
◦ 1日3800歩程度のウォーキングでも認知症のリスクが約25%低下することが研究で分かっています。また、歩数が増えるほど認知症のリスクは低下し、1日約1万歩で最もリスクが低下しますが、1万歩を超えて歩きすぎると効果が弱まる可能性があるとも述べられています。
• 座りすぎと認知症リスクに関する研究
◦ 海外の論文では、1日10時間以上座っていると認知症のリスクが上がるとされています。
• 脳の萎縮と運動に関する研究
◦ 日本人を対象とした研究では、男性において1日の歩数が多いグループの人の前頭葉の脳の萎縮が、最も歩数が少ないグループの約3分の1だったという結果や、女性ではエネルギー消費量が多い方が脳が萎縮していなかったというデータがあります。
• 食事の多様性と認知機能に関する研究
◦ 日本人を対象とした研究で、多様な食材を摂取している人は、認知機能が低下しにくいことが分かっています。これは、特定の成分だけでなく、食品に含まれる微量な栄養素など「雑多な栄養」を取り込むことが健康に良いという考えに基づいています。
• MIND食(マインド食)
◦ MIND食は、地中海式食事法とDASH食(高血圧改善食)の良いとこ取りをした食事法で、世界で最も健康的な食事と呼ばれています。MIND食の要素を取り入れることで、認知症の発症リスクが約50%低くなるというデータも紹介されています。
• 耳垢除去と認知機能に関する研究
◦ アメリカの高齢者向け施設での研究では、入居者の耳垢の詰まりを取り除くことで聴力だけでなく認知機能も改善したと報告されています。日本の研究でも、耳垢が詰まって聴力が悪くなっている人は平均7デシベル聴力が低下しているという事実が分かっています。
• 難聴と認知症リスクに関する研究
◦ 聴力が衰えると、脳の記憶を管理する海馬や側頭葉が縮むことにつながるため、難聴は認知症のリスクであるとされています。
• 睡眠時間と脳の萎縮・認知機能に関する研究
◦ シンガポール国立大学の研究では、睡眠時間が1時間短いだけで、脳室(脳が萎縮した結果拡大する場所)が1年ごとに0.55%ずつ拡大し、認知機能も年々低下したと報告されています。
◦ 福岡県の住民を対象とした研究では、5時間未満と10時間以上の睡眠で認知症のリスクが上がることが示されています。また、北欧の研究でも9時間以上の睡眠で認知症のリスクが上昇したというデータがあり、推奨される睡眠時間は約7時間とされています。
• 昼寝と認知症リスクに関する研究
◦ 60分以内の昼寝はアルツハイマー型認知症のリスクを下げたのに対し、60分以上の昼寝はリスクを高めたという論文が紹介されています。アメリカで行われた研究でも、昼寝の時間が長いほど記憶力の低下が認められたとされています。
これらの研究や概念は、運動、食事、睡眠、聴覚といった多角的なアプローチが脳の老化予防に重要であることを示しています。
#スーパーエイジャー
#脳の老化予防
#アンチエイジング
#筋トレ
#健康寿命
#認知症予防
#MICタンパク質
#食の多様性
#運動習慣
#細胞が若返る
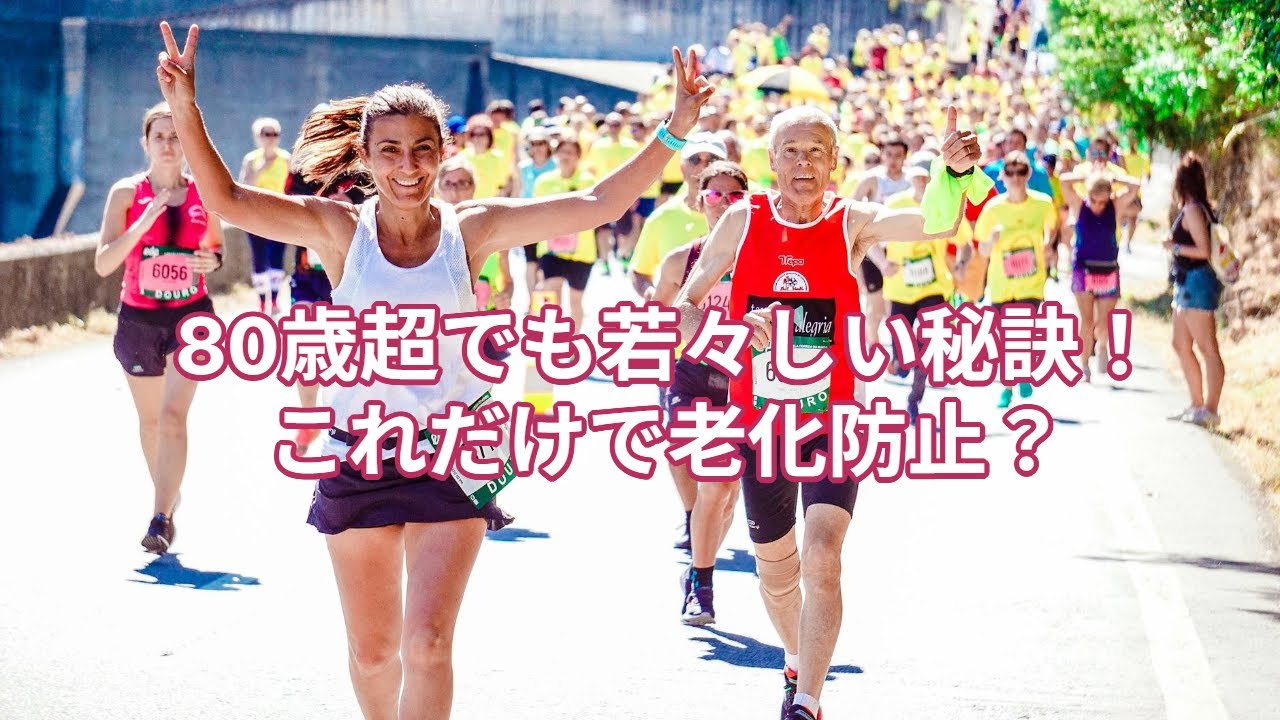


コメント